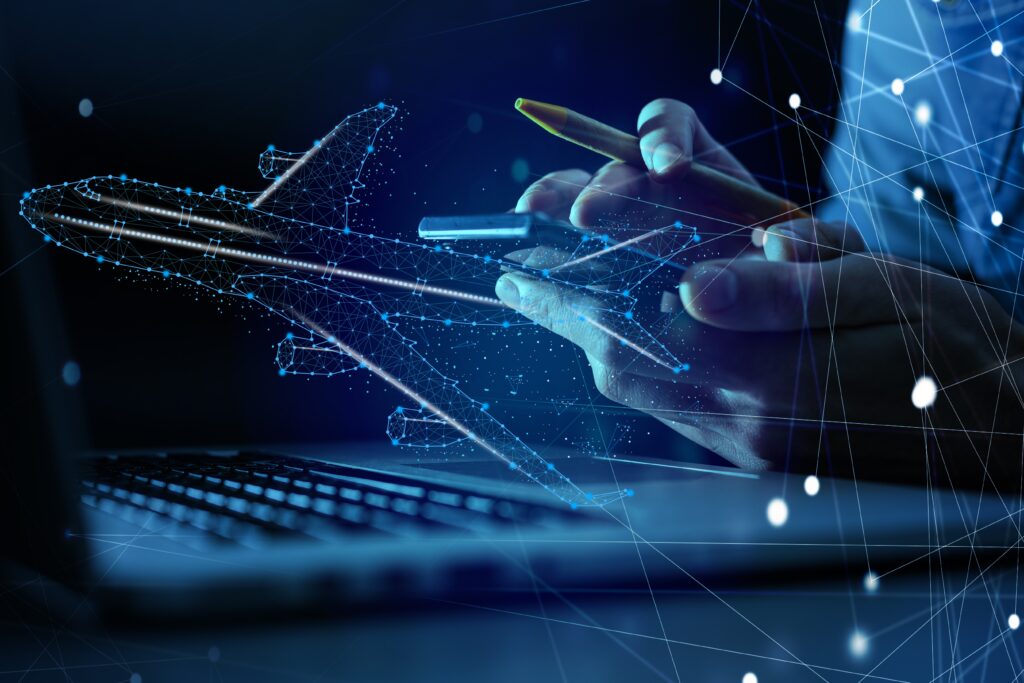業務委託人材が、後に勤務を訴えてくる時代
市場の動向として、SNS操作やライター編集、コンテンツ作成などを外部に委託する企業が増えています。しかし、その委託者が「自分は雇用された社員だ」と主張し、勤務賃金の6ヶ月分、社会保険の勝手な置換、そして「セクハラを受けた」とすら言い出す事案が急増しています。
実際、異業種間のSNS運用委託においても、無約にて本社へ訴訟が展開された例があります。それらは、LINEやInstagramのスクリーンショットを証拠に「期間中は勤務していた」「社長から指示があった」と主張し、勝手に決めた時間シートを提出して、資格不明な勤務賃金を請求してきたのです。
【問題の本質についての分析】
現代社会では、雇用と委託の境界が薄くなり、誰もが主張で「自分は就業していた」と言い出せる時代です。書面上は委託契約であったとしても、作業指示があり、出社日や勤務時間が別に定められていたならば、「実質的に雇用」と判断される可能性があります。
また、SNSやLINEのトークは気軽なやりとりが多いため、結構な頼み事も「指示」「命令」と捉えられ、判断の主当とされる恐れがあります。
【ディフェンス・カンパニーが提供する解決策】
〇 委託合意書(契約書)の締結
委託開始前に、業務の範囲、代謝、期間、連絡方法を明文化し、特に「作業日時は自由である」ことを明示することが重要です。作業日時を指定すると、それを指揮命令と主張されるからです。
〇 「指示」「依頼」の言語選択に注意
たとえ業務委託であっても、「指示しておいて」「この日は出て」などの表現は、支配・従属関係と見なされるおそれがあります。「ご一考ください」「ご協力いただけますと幸いです」などの柔らかい表現を用い、命令的ニュアンスを排除する工夫が必要です。
〇 SNSのトークは全部ログ化して保存する
LINEやInstagramでのやりとりは、後の証拠になると同時に、捉え方による「勤務」の定義の危険性も持ちます。自体は安易な通信手段でも、全ログ化して第三者にも扱えるよう整備しておくことで、伝え方の正確性を確保します。
〇 委託委員との通信は「企業メール」で統一
LINEやSNSは個人情報の混同や勤務証拠になりやすいため、通信は可能な限り公式ツールに統一し、後日の約束性を高めます。
〇 相手方からの請求書と支払明細を確実に保管・精査する
当初から業務委託として始まっているのであれば、「雇用ではない」ことを立証する決定的証拠となるのが、相手から提出された請求書および当社からの報酬支払明細です。これらを時系列で整え、支払いが給与でなく業務報酬として処理されていることを明確化し、証拠能力を高めます。
〇 月次評価やレポートのような「勤務的行動」を記録しない
委託委員の勤務を体系化して記録すること自体が雇用的であるため、作成は最小限にとどめ、分析や感想の交換の程度に減量します。
〇 「委託である」ことを再確認する総括メールを期間中に送信
過去のログや依頼内容を整理して、定期的に「委託の範囲を転言しない」ことを明文化したメールを送信しておくことで、後日の意見連続を防げます。
【法的根拠と解説~当社顧問弁護士の見解】
〇 最高裁判所判決(最判平成12年3月9日)
『合意の形式や名称に関係なく、実質的な勤務形態をもって判断する』
この判例は、書面上の合意や名称に従わず、実際にどのような作業の実態があったかによって、雇用と判断されるとする「実質成立語法」を確立させた重要判例です。
この判例の指針によれば、本条のようなSNS委託であっても、会社側が指示を繰り返し、日時や勤務に定めがあるならば、判断の上では「雇用」と解釈される恐れがあるのです。
【おわりに】
業務委託は現代社会の人材派遣スタイルの一つですが、その前提には「明確な分離」が必要です。
悪意のある委託委員ほど、もし合意が曖昧ならば「後で算段」とばかりに、あることないことを言い出してきます。
約束された合意、成形化された作業経過、第三者も認められる通信経路。
これらの「三丸」があるかないかで、会社の危機は大きく違います。
ディフェンス・カンパニーは、固ゆるな合意、ログ、記録のトライアングルにより、あなたの会社を譲らぬ危機から守ります。
ディフェンス・カンパニーは、困っている人、企業、社会に手を差し伸べる存在であり続けます。
【ディフェンス・カンパニーの格言】
合意なき手は、後の戦場を支配す
文書で安易にしたことが、いずれ法律戦の皆殺場となる。合意の不備えは、危機管理の不採点である。
【注意書き】
※本記事は、危機管理コンサルタントとしての見解を示したものであり、法的助言や法律事務の提供を目的とするものではありません。法的判断が必要な場合は、当社の顧問弁護士をご紹介させていただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。